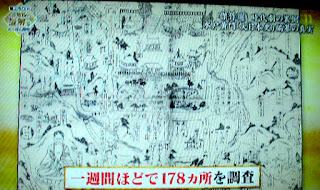坂本龍馬が北海道(当時は蝦夷地)に興味をもつようになったのは、脱藩後勝海舟に出逢い海軍操練所に入って、勝の手伝いをしているうちに、多くの北海道情報を得たからである。
そして蝦夷地に乗り込むつもりで、妻と蝦夷語を学んでいた。
 |
| おりょうが持っていた蝦夷語の本 |
 |
| 北海道の竜馬像 |
【1】 蝦夷地移住計画
1864年6月初旬には、京都・摂津の浪人を幕府の軍艦「黒龍丸」に乗せて蝦夷地を目指す計画を勝海舟に提案している。
蝦夷へ移住し、開拓事業を起こすのが目的であった。
 |
| 移住計画 |
しかしその直後、池田屋事件が発生。
勝や龍馬に蝦夷地の情報を話をしていた北添佶磨(きたぞえ・きつま)や、神戸海軍操練所の塾生であった望月亀弥太が池田屋事件に含まれていたことから、勝海舟に迷惑がかかると判断した龍馬はこの蝦夷地移住計画を断念した。
龍馬にとってはさぞ無念だったろう。
竜馬は船との縁が薄く、最初に手に入れたワイル・ウエフ号
(亀山社中の練習船で、薩摩藩の援助を得て、グラバーから購入したプロイセン建造の木造小型帆船)は1866年(慶応2年)4月28日 長崎を出航し、鹿児島へ向かっていたが、途中暴風雨に遭遇し、長崎県中通島の東、潮合崎沖で暗礁に乗り上げ転覆し、亀山社中の池内蔵太など、乗組員の多くが死亡した。
この時、龍馬の頭の中にあったのは、次のような計画であった。
(1)蝦夷地開拓により、さまざまな資源開発を行う。石炭・林業・農業・漁業など、当時はまだほとんど手付かずであった産業を起こせると考えた。
(2)大阪で商業活動をしていたメンバーと合同で(陸奥陽之助や高松太郎ら)、大阪に営業拠点を置き、蝦夷地の資源開発で得た物産を「蝦夷-大坂-馬関-長崎」の物流に乗せる。
常識的には、「江戸-大坂ライン」や「馬関-大坂ライン」あたりの主要航路で既存の物流競争に勝とうと考えるが、龍馬の発想は大きい。
(A) 北添 佶摩(きたぞえ きつま)
土佐藩高岡郡岩目地(いわめじ)村の庄屋北添与五郎の五男。16歳で庄屋職をつぎ、19歳のとき高北九ヶ村の大庄屋となる。
開国に反対して攘夷を唱え、文久3年(1863年)、本山七郎を名乗って江戸へ出て、大橋正寿の門人となり同志と共に学ぶ。
勝や龍馬に蝦夷地の情報を話をしていた北添佶磨(きたぞえ・きつま)や、神戸海軍操練所の塾生であった望月亀弥太が池田屋事件に含まれていたことから、勝海舟に迷惑がかかると判断した龍馬はこの蝦夷地移住計画を断念した。
龍馬にとってはさぞ無念だったろう。
【2】 蝦夷地交易計画
その後蝦夷地交易計画をたてるが、まず活動の命である船舶の入手をしなければならない。
(亀山社中の練習船で、薩摩藩の援助を得て、グラバーから購入したプロイセン建造の木造小型帆船)は1866年(慶応2年)4月28日 長崎を出航し、鹿児島へ向かっていたが、途中暴風雨に遭遇し、長崎県中通島の東、潮合崎沖で暗礁に乗り上げ転覆し、亀山社中の池内蔵太など、乗組員の多くが死亡した。
交易計画では、龍馬はプロシア商人チョルチーと交渉し「大極丸」という船を手に入れる。後述する船の支払い問題を抱えながらも、大極丸は動き出す。
この時、龍馬の頭の中にあったのは、次のような計画であった。
(1)蝦夷地開拓により、さまざまな資源開発を行う。石炭・林業・農業・漁業など、当時はまだほとんど手付かずであった産業を起こせると考えた。
(2)大阪で商業活動をしていたメンバーと合同で(陸奥陽之助や高松太郎ら)、大阪に営業拠点を置き、蝦夷地の資源開発で得た物産を「蝦夷-大坂-馬関-長崎」の物流に乗せる。
常識的には、「江戸-大坂ライン」や「馬関-大坂ライン」あたりの主要航路で既存の物流競争に勝とうと考えるが、龍馬の発想は大きい。
しかし…この計画は暗礁に乗り上げる。
大極丸の代金を、龍馬は近江商人から借り受ける予定でいたのだが結局お金は工面できず、大極丸は差し押さえられ運行不可能になった。
次の手として、亀山社中が船乗りをリース(人材派遣)していた大洲藩(今の愛媛県)所有の「いろは丸」の賃貸契約を進め、海援隊になったあと、ようやく契約が成り、いろは丸が亀山社中を運行するという初航海で、例の「いろは丸事件」が起き、この船もワイルウェフ号同様、亀山社中の手に渡ったとたん沈没してしまった。
次の手として、亀山社中が船乗りをリース(人材派遣)していた大洲藩(今の愛媛県)所有の「いろは丸」の賃貸契約を進め、海援隊になったあと、ようやく契約が成り、いろは丸が亀山社中を運行するという初航海で、例の「いろは丸事件」が起き、この船もワイルウェフ号同様、亀山社中の手に渡ったとたん沈没してしまった。
別のブログに書いたように、紀州藩からの賠償金交渉には成功したが、その直後に竜馬は暗殺されて、すべての計画は挫折した。
蝦夷開拓情報を勝や坂本に伝えた人物
幕末期、蝦夷地には海獣の毛皮獲得を主たる目的にロシアが侵入しており、蝦夷地の防衛は急務であった。そんな中、当時の箱館には徳川幕府のみならず全国諸藩から様々な人々が訪れていた。ここではそのうちの二人を記載する。
(A) 北添 佶摩(きたぞえ きつま)
土佐藩高岡郡岩目地(いわめじ)村の庄屋北添与五郎の五男。16歳で庄屋職をつぎ、19歳のとき高北九ヶ村の大庄屋となる。
開国に反対して攘夷を唱え、文久3年(1863年)、本山七郎を名乗って江戸へ出て、大橋正寿の門人となり同志と共に学ぶ。
なお、この策には坂本龍馬が一枚かんでいたとみられ、事実、龍馬は計画実現のために大久保一翁などに働きかけている。
その後、所属していた神戸海軍操練所の塾頭であった坂本龍馬に過激な尊皇攘夷派とは交流を絶つべきであると諭されたにも関わらず、同じく土佐出身の望月亀弥太らと京都へ赴いて公卿達と面会を重ねたが、元治元年(1864年)の池田屋事件に遭遇し死亡した。この際、新選組によって殺害されたと思われていたが、近年の研究によって自害して果てたことが判明している。享年30。
しかし、残念ながら北添は池田屋事件で死亡、龍馬の第一次蝦夷地開拓計画も中止に追い込まれた。ちなみに、北添は蝦夷地視察に際して3人の親友を誘い、同行したといわれており、そのうちの一人、小松小太郎は箱館への渡航中に病気になり、看護の甲斐なく箱館上陸後に亡くなり、遺体は函館山麓(現在の住吉町共同墓地内)に埋葬された。
発病当時、北添らは小松に下船するよう説得したが、小松は「死んでも北海の守護神になる」と聞き入れなかった。当時、蝦夷地に渡るということは命懸けの行動でした。
(B)望月 亀弥太(もちづき かめやた)
その後、所属していた神戸海軍操練所の塾頭であった坂本龍馬に過激な尊皇攘夷派とは交流を絶つべきであると諭されたにも関わらず、同じく土佐出身の望月亀弥太らと京都へ赴いて公卿達と面会を重ねたが、元治元年(1864年)の池田屋事件に遭遇し死亡した。この際、新選組によって殺害されたと思われていたが、近年の研究によって自害して果てたことが判明している。享年30。
しかし、残念ながら北添は池田屋事件で死亡、龍馬の第一次蝦夷地開拓計画も中止に追い込まれた。ちなみに、北添は蝦夷地視察に際して3人の親友を誘い、同行したといわれており、そのうちの一人、小松小太郎は箱館への渡航中に病気になり、看護の甲斐なく箱館上陸後に亡くなり、遺体は函館山麓(現在の住吉町共同墓地内)に埋葬された。
発病当時、北添らは小松に下船するよう説得したが、小松は「死んでも北海の守護神になる」と聞き入れなかった。当時、蝦夷地に渡るということは命懸けの行動でした。
(B)望月 亀弥太(もちづき かめやた)
幕末の土佐藩士で、土佐勤皇党の一人。神戸海軍操練所生。諱は義澄。
文久元年(1861年)、兄・望月清平と共に武市半平太の尊皇攘夷思想に賛同して土佐勤王党に加盟し、文久2年(1862年)10月、尊攘派組織五十人組の一人として、江戸へ向かう旧藩主山内容堂に従って上洛する。
文久3年(1863年)、藩命を受けて幕臣・勝海舟の下で航海術を学び、その後、坂本龍馬の紹介で勝が総監を務める神戸海軍操練所へ入所するが、元治元年(1864年)、藩より帰国命令が出されたため脱藩して長州藩邸に潜伏。長州藩の過激尊皇志士達と交流を続けていたため、池田屋事件に遭遇した。池田屋を脱出した望月は幕府方諸藩兵によって取り囲まれて深手を負い、かろうじて長州藩邸に辿り着いたものの中へ入る事を許されずに門前で自刃した。享年27。
坂本龍馬も勝海舟も、この二人の死を嘆いた。
文久元年(1861年)、兄・望月清平と共に武市半平太の尊皇攘夷思想に賛同して土佐勤王党に加盟し、文久2年(1862年)10月、尊攘派組織五十人組の一人として、江戸へ向かう旧藩主山内容堂に従って上洛する。
文久3年(1863年)、藩命を受けて幕臣・勝海舟の下で航海術を学び、その後、坂本龍馬の紹介で勝が総監を務める神戸海軍操練所へ入所するが、元治元年(1864年)、藩より帰国命令が出されたため脱藩して長州藩邸に潜伏。長州藩の過激尊皇志士達と交流を続けていたため、池田屋事件に遭遇した。池田屋を脱出した望月は幕府方諸藩兵によって取り囲まれて深手を負い、かろうじて長州藩邸に辿り着いたものの中へ入る事を許されずに門前で自刃した。享年27。
坂本龍馬も勝海舟も、この二人の死を嘆いた。