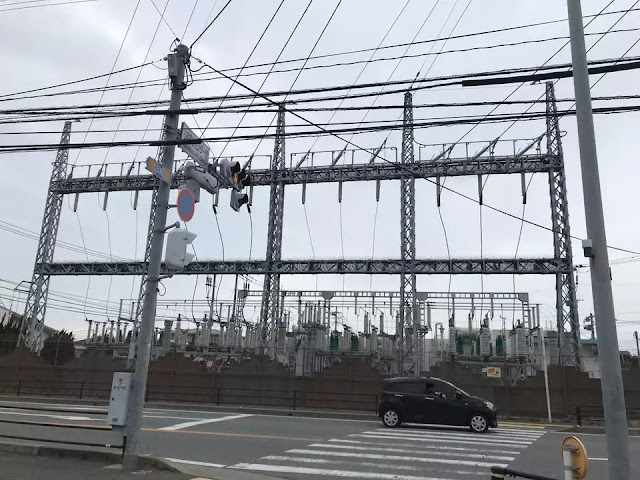徳川家康の大河ドラマで有名になった三河の国。3本の河が流れている領域を連想していたが、そうではないようだ。
国郡制の時期に愛知県東部に設定された国名。参州(さんしゅう)。東海道15か国の一つ。
東は遠江(とおとうみ)国(静岡県)、北は信濃(しなの)(長野県)・美濃(みの)(岐阜県)の両国、西の北半は尾張(おわり)国(愛知県)に接している。
当国は北部山岳地帯としての奥三河、その地帯より源を発し、東部、西部をそれぞれ貫流する豊川(とよがわ)流域平野の東三河と矢作(やはぎ)川流域平野の西三河、さらに遠州灘(えんしゅうなだ)と伊勢(いせ)湾を東西に画し、志摩半島の志摩国(三重県)と相対する渥美(あつみ)半島の4地域に分かつことができる。4地域とも風土的・歴史的地域差をもつが、方言に端的に示されるように総体としては尾張とはかなり異なる東国的な文化圏を発展させてきた。
三河の語源については、三つの川があったからとか、加茂(かも)の神の御川(みかわ)の義であるとかの説はあるが、通説というべきものはない。
先史時代の歴史を物語る資料としては、まず豊橋市牛川(うしかわ)町で発見された成人女性の左上腕骨と成人男性の大腿(だいたい)骨片の化石人骨がある。牛川人と名づけられた人骨はいずれも約10万年前の中期洪積世の旧人と鑑定され、いまも論争の続いている明石(あかし)原人を別とすれば、日本最古の人類である。
縄文時代の遺跡としては大量の人骨が発掘された吉胡(よしご)貝塚が、また弥生(やよい)時代では豊川河口近くの豊橋市瓜郷(うりごう)遺跡などがあり、豊川(とよかわ)市篠束(しのづか)町の篠束遺跡は三河以東での最初の農村遺跡として名高い。
9世紀ごろに編纂(へんさん)された『国造本紀(こくぞうほんぎ)』によれば、三河は古く三河と穂(ほ)の二つのクニに分かれ、それぞれ三河国造(くにのみやつこ)、穂国造が支配していたが、豊川市国府(こう)町所在の全長96メートルの船山古墳に象徴されるように、東三河の豪族の力が強大となり、国衙(こくが)は穂のクニに置かれることとなった。令(りょう)制では上国、『延喜式(えんぎしき)』では近国に位置づけられ、加茂、額田(ぬかだ)、碧海(あおみ)、幡豆(はず)、宝飫(ほお)、八名(やな)、渥美の7郡に分ける。このうち903年(延喜3)宝飫の北部を割いて設楽(したら)郡を設置した。国府および国分寺はともに豊川市内にあった。
平安時代には伊勢神宮との関係深く、1192年(建久3)には12か所に神戸(かんべ)、御厨(みくりや)、御園(みその)があった。鎌倉期には公武両勢力の接点となる。守護の初見は安達盛長(あだちもりなが)。承久(じょうきゅう)の乱(1221)後は足利(あしかが)氏の世襲となり、斯波(しば)、一色(いっしき)、細川、仁木(にき)、今川氏などその一族被官(ひかん)の本拠となった。
彼らは南北朝時代の内乱に戦功をたて、管領(かんれい)や侍所頭人(さむらいどころとうにん)など室町幕府の要職につく。室町期の守護は仁木義長(よしなが)が初代、大島義高(よしたか)、一色範光(のりみつ)、一色詮範(あきのり)、細川持常(もちつね)、同成之(しげゆき)、一色義直(よしなお)と受け継がれて戦国時代を迎える。
15世紀中葉から、加茂郡松平村より出た松平氏が台頭し、3代信光は碧海郡安祥(あんじょう)城、松平氏7代清康(きよやす)は岡崎城を拠点として西三河に勢力を広めた。松平氏8代広忠(ひろただ)の時期、三河は東西から今川、織田両氏の侵入にあい、広忠は今川義元(よしもと)と盟約しながら岡崎城1城を保つにすぎなかったが、その子徳川家康は、今川義元が桶狭間(おけはざま)合戦に敗死後、織田信長と同盟を結んで東進し、1590年(天正18)関東に転封する。
関ヶ原役後、家康は松平家清を吉田(豊橋):7万石、本多康重(やすしげ)を岡崎:5万石、本多康俊を西尾:6万石で置き、三宅、戸田、大岡、内藤、土井などの譜代(ふだい)大名を創設したほか、多くの旗本領、直轄領を設定した。
細分割支配の特色は江戸時代を通じて受け継がれ、三河の開発に大きな影響を与えた。
維新時の幕府直轄領は三河県となったが、伊奈(いな)県に合併、また10藩あった藩領域は額田県となり、1872年(明治5)に両地域とも愛知県に編入された。
三河地方は古代から良質のあしぎぬの産地として知られていたが、早くも16世紀からは木綿が栽培される。近世では所領関係が複雑なため、水田開発は比較的後れたが、「三河木綿」の名があるように木綿の名産地であった。
[所理喜夫]
 昭和28年6月4日から降りはじめた雨は29日まで続き、古賀で最大の水害となった。
昭和28年6月4日から降りはじめた雨は29日まで続き、古賀で最大の水害となった。